夜の長崎港は、船の灯が静かに水面を揺らしていた。
梓は祖母の遺品から見つけた硝子片を掌にのせ、港の光にかざしてみた。
青と赤が混ざり合い、きらめきが夜の波に重なる。
数日前、美術館で神父が言った言葉が蘇る。
――割れても、光を通す。
その通りだ。
欠けた硝子でも、確かに光を掬い、色を宿す。
机に広げた祖母の古い手紙を見返す。
そこには「北へ」「港」「硝子」という断片が繰り返し書かれていた。
そして最後の一枚。滲んだインクの行間に、小さな押印があった。
《札幌 教会》
薄れて判読しづらいが、確かにそう刻まれている。
梓の胸に冷たい衝撃が走った。
祖母が待っていたのは、長崎の地で出会った「札幌から来た人」だったのだ。
その人が携えていたステンドグラスの破片――。
祖母は約束を果たせなかった代わりに、その硝子を遺した。
「おばあちゃん……」
梓はそっと硝子片を光に透かした。
壁に映った色は、不完全ながらも鮮やかに広がった。
祖母が伝えられなかった想いは、確かにここに残っている。
兄・智彦が帰ってきて、梓の横に立った。
「まだ、その硝子を持ってたのか」
「うん。でも、これはただの欠片じゃない。祖母が残した記憶だよ」
智彦はしばらく黙り、やがて小さくうなずいた。
「……札幌に行くのか」
「ええ。行かなくちゃ。祖母の代わりに」
硝子片をポケットにしまい、梓は宍道湖ではなく、北の空を思い描いた。
札幌の教会。その窓に、かつては同じ硝子が嵌め込まれていたはず。
そこへ行けば、祖母が果たせなかった“記憶の旅”がつながるのだろう。
夜風が吹き、港の灯りがまた揺れた。
その揺らぎの中に、梓は確かに祖母の影を見た。
欠けても消えない光は、これから彼女自身を導いていくのだ。
.fin
第12週 『消えた宛先の灯』next>> 第1話 ― 郵便資料室
<< Previous 第4話 ― 光の記憶
紙袋の行方
第1週 『見えない鍵』
第2週 『名前のない約束』
第3週 『宿帳の余白』
第4週 『買い取ってない品』
第5週 『願いは誰のもの』
第6週 『二人で書いた誓い』
第7週 『割れた陶片の先』
第8週 『夕立ちの残響』
第9週 『消えた宛名』
第10週 『影送りの窓』
第11週 『記憶を映す硝子』
第12週 『消えた宛先の灯』
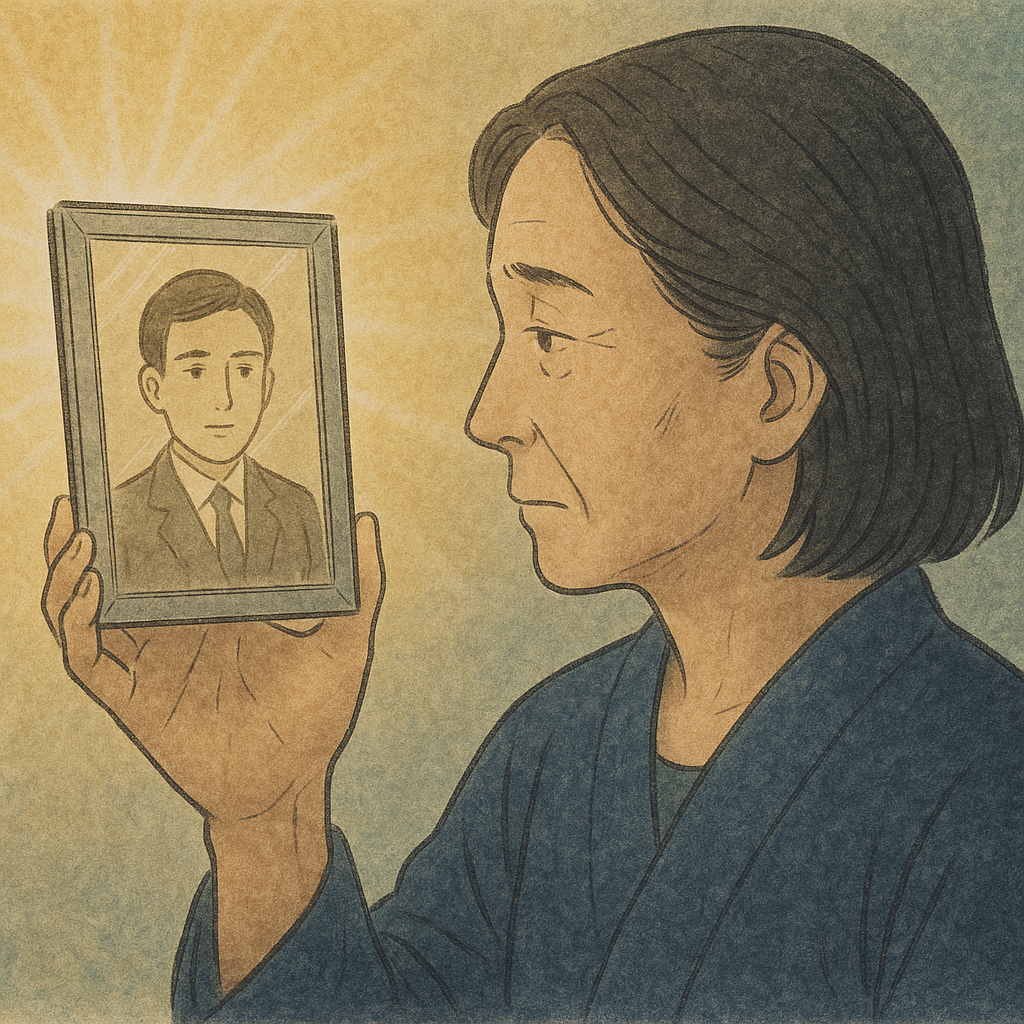
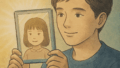

コメント