硝子片を小箱にしまった翌日、梓は再び祖母の家に足を運んだ。
午前の光が差し込む物置の中は、埃が舞い、古い紙の匂いが濃く漂っている。
昨日見つけた箱の下に、もうひとつ重たい段ボールがあった。
中には、古びた布に包まれた手紙の束があった。
封筒の色は黄ばんでいて、インクも滲んでいる。差出人の名前はなく、宛名も「宮本」と苗字だけ。
便箋を一枚ずつ広げると、断片的な言葉が目に飛び込んできた。
――「港の明かり」
――「硝子の光」
――「北へ行く日」
文章はどれも短く、具体的な内容はぼやけている。
まるで、誰かに気づかれないように暗号のように書かれた手紙だった。
梓は震える指で、最後の一枚を取り出した。
そこにはこう記されていた。
《次に会うとき、硝子を持っていく。北の地で待っている。》
「……硝子」
思わず声に出す。昨日見つけたステンドグラスの欠片と、この手紙の言葉が結びつく。
祖母はかつて、誰かから硝子を託されていたのだろうか。
そして“北の地”とは――札幌。
そのとき、戸口から兄・智彦の声が飛んだ。
「また何か見つけたのか?」
振り返ると、腕を組んだ兄が険しい顔で立っていた。
「兄さん……祖母は、札幌の人と何か繋がりがあったんじゃない?」
「くだらない。古い手紙に踊らされるな」
「でも、硝子も、この言葉も……」
智彦は苛立ったように顔を背けた。
「掘り返したって意味はない。祖母は何も語らずに逝ったんだ。それが答えだ」
言い捨てるように去っていく兄の背中を見送りながら、梓は手紙を抱きしめた。
――語らなかったのは、語れなかったから。
そう思えてならなかった。
硝子片と手紙。二つの断片は、確実に祖母の“もうひとつの人生”を示している。
梓は決意した。
次に会いに行くべきは、祖母のことを誰よりもよく知っている人――祖母の古い友人、藤堂幸代だ。
next>> 第3話 ― 幸代の証言 ー
<< Previous 第1話 ― 割れた硝子 ―
紙袋の行方
第1週 『見えない鍵』
第2週 『名前のない約束』
第3週 『宿帳の余白』
第4週 『買い取ってない品』
第5週 『願いは誰のもの』
第6週 『二人で書いた誓い』
第7週 『割れた陶片の先』
第8週 『夕立ちの残響』
第9週 『消えた宛名』
第10週 『影送りの窓』
第11週 『記憶を映す硝子』
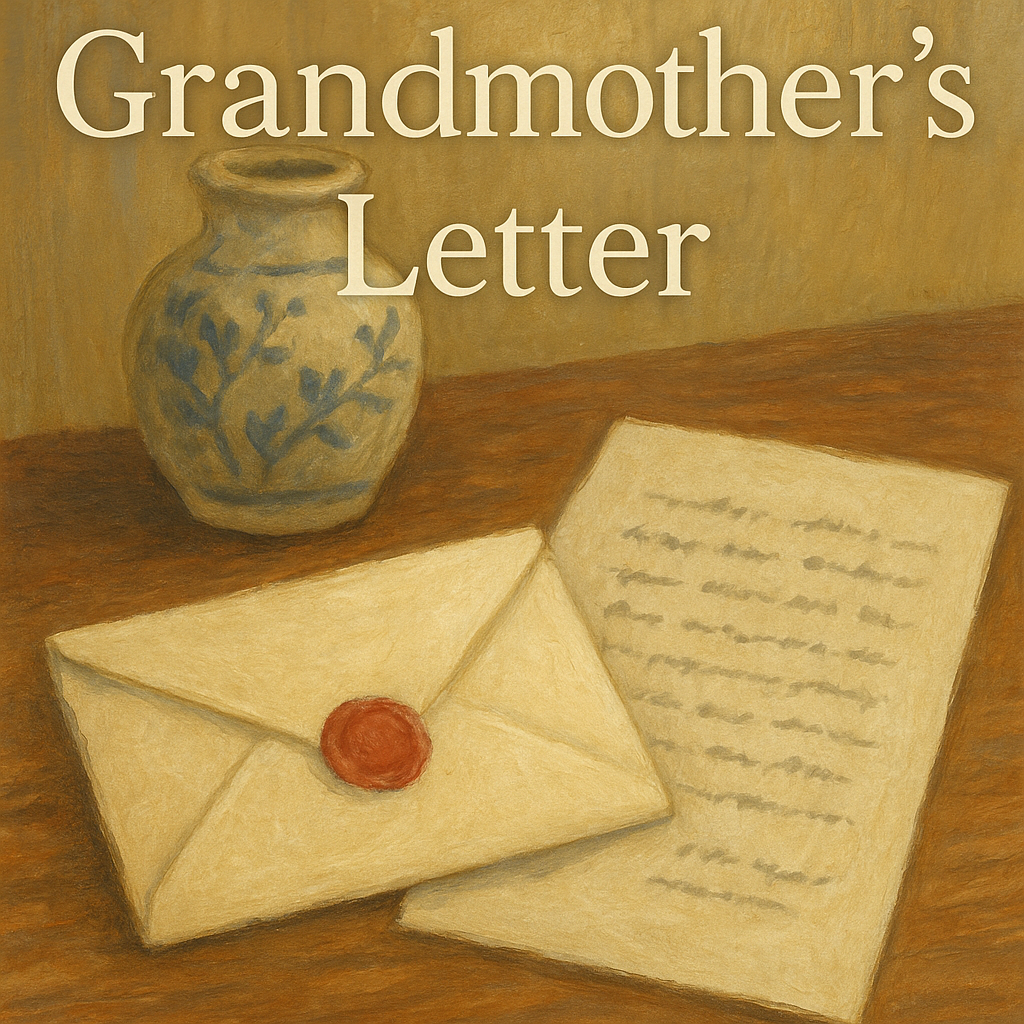


コメント