夜の鶴岡の街に、柔らかな灯りがともっていた。
商店街の軒先には和紙の灯籠がずらりと並び、ひとつひとつに手書きの文字や絵が描かれている。
梓はその灯籠の列の中を、風間を取材しているという青年――榊原 悠人と並んで歩いていた。
「風間信一は、札幌の教会でステンドグラスの修復に関わっていた人です。戦後すぐに、ガラス片を持って南へ旅をしていたと記録にあります」
梓は思わず足を止めた。
「……やっぱり」
「ご存じなんですか?」
「祖母が、札幌からの硝子片を大切に持っていたんです。宛名を消された手紙も、その人からかもしれません」
灯籠の光が二人の顔を照らし、ゆらゆらと影を揺らした。
悠人は手帳を開き、一枚の古い写真を見せた。
そこには若い男性が写っている。背後に映るのは札幌の古い教会だった。
「この人が風間信一。彼は“風の便り”という名で旅の記録を残していました」
「風の便り……?」
「届かない手紙でも、風に託せばいつか届く――そう信じていたらしいです」
その言葉に、梓の胸が熱くなった。
宛名を消された封筒、そして届かなかった手紙。
それでも風間は“届く”と信じていた。
ふと風が吹き抜け、灯籠の灯が小さく揺れた。
光が封筒の紙を透かし、梓の指先に柔らかな熱を残した。
「……おばあちゃんは、この灯を知ってたのかな」
「きっと見ていたと思います」
悠人の声は穏やかだった。
風の夜、無数の灯籠が揺れる通りで、梓は初めて静かな確信を覚えた。
祖母の旅は、まだ終わっていない。
風のように受け継がれ、今、自分の手の中に続いている。
next>> 第4話 ― 手紙の声
<< Previous 第2話 ― 風の通り道
紙袋の行方
第1週 『見えない鍵』
第2週 『名前のない約束』
第3週 『宿帳の余白』
第4週 『買い取ってない品』
第5週 『願いは誰のもの』
第6週 『二人で書いた誓い』
第7週 『割れた陶片の先』
第8週 『夕立ちの残響』
第9週 『消えた宛名』
第10週 『影送りの窓』
第11週 『記憶を映す硝子』
第12週 『消えた宛先の灯』
第13週 『風の便り』


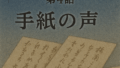
コメント