その週の金曜、図書館の休憩室で梢は冷たい麦茶を飲んでいた。
午前中は夏休みの子どもたちで賑わい、ようやく訪れた静けさだった。
そこへ、休憩室のドアが軽くノックされ、同僚が顔を覗かせる。
「梢さん、お客さん来てるよ。商店街の朋美さんが一緒」
外に出ると、朋美が手を振っていた。
その隣に立つ長身の男性――森本翔だった。
日焼けした肌に、東京の空気を纏ったような落ち着きがある。
けれど、笑ったときの目尻の皺は、高校時代と変わらない。
「……久しぶりだね」
翔の声は、記憶より少し低くなっていた。
それでも耳に残る響きは、あのカセットの声に重なる気がする。
梢は胸の奥がざわつくのを感じた。
近くの喫茶店に移動し、アイスコーヒーを頼む。
翔は、東京で音響の仕事をしていること、今は夏休みを利用して帰省していることを話した。
「この前、たまたま朋美に会ってさ。梢の話になって……懐かしくなった」
「そうなんだ」
梢はタイミングを見計らい、鞄から小さなケースを取り出した。
透明のケース越しに見えるカセットテープ。
翔が目を細める。
「これ……懐かしいな。放送部の?」
「図書館の倉庫で見つけたの。再生したら……声が入ってた」
「声?」
梢は一瞬躊躇い、でも目を逸らさずに言った。
「雨の音と……“ずっと好きだった”って。最後に“小樽でまた”って」
翔の指先が、カップの縁で止まった。
「……そう」
「翔くんの声じゃない?」
数秒の沈黙のあと、彼はかすかに笑った。
「俺の声に聞こえた?」
「……うん」
「違うよ。俺じゃない」
否定は軽く、冗談のように聞こえた。
でも、その瞬間、翔の視線がほんの少し泳いだのを、梢は見逃さなかった。
「まあ、放送部には男が何人かいたしな。覚えてる?」
「……はっきりは」
「じゃあ、その声の人を探してみればいい。答えが出るかも」
それ以上は何も言わず、翔は話題を変えた。
高校の文化祭の思い出、顧問の口癖、部室の窓から見えたグラウンドの夕立。
その中で、梢の記憶は少しずつあの日に近づいていく――けれど、肝心な部分はまだ霧の中だった。
店を出ると、空は薄く曇り、川面を渡る風が湿っていた。
翔は「また会おう」と短く言い、商店街の角を曲がっていった。
背中が見えなくなるまで、梢は立ち尽くした。
ポケットの中のカセットが、じわりと熱を持っているように感じられた。
next>> 第4話 ― 舟の上の沈黙 ―
<< Previous 第2話 ― 記憶の断片 ―
紙袋の行方
第1週 『見えない鍵』
第2週 『名前のない約束』
第3週 『宿帳の余白』
第4週 『買い取ってない品』
第5週 『願いは誰のもの』
第6週 『二人で書いた誓い』
第7週 『割れた陶片の先』
第8週 『夕立ちの残響』
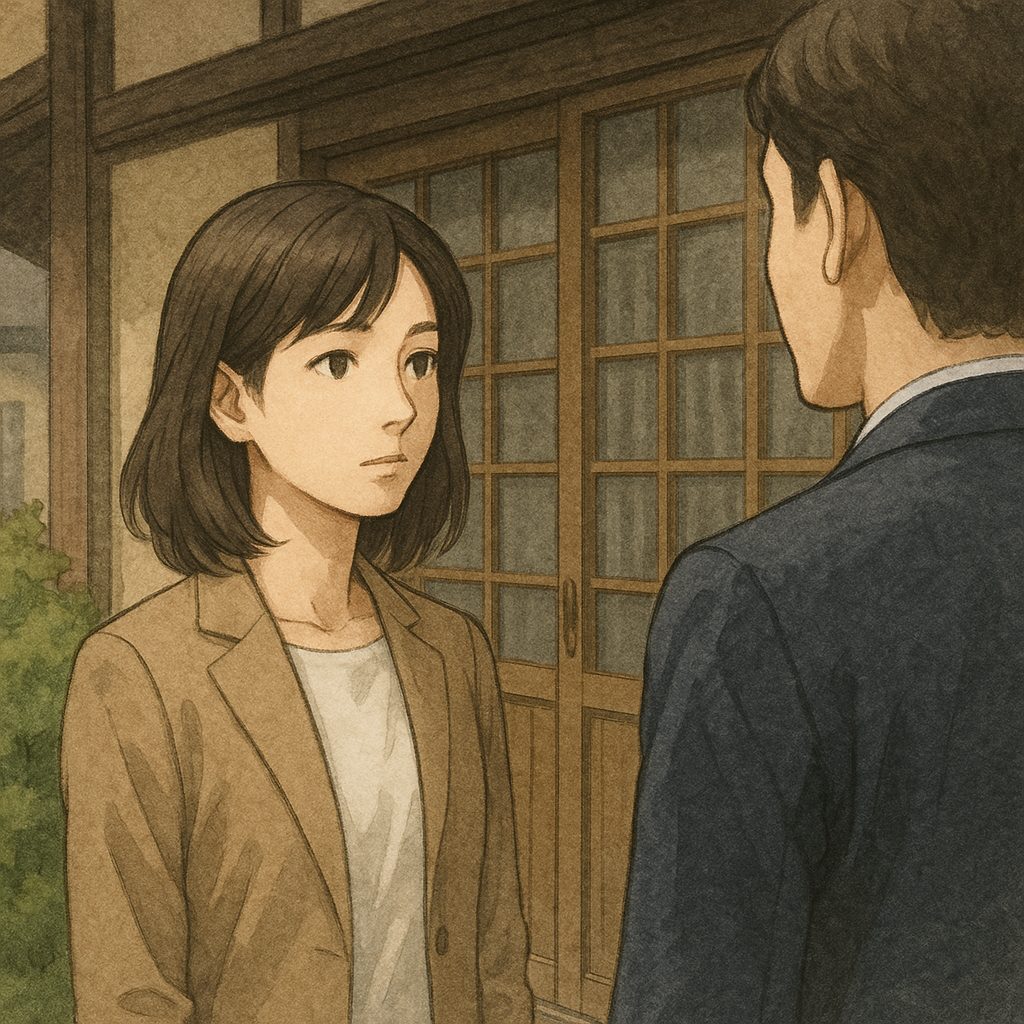


コメント