高岡の空は、朝から薄い鉛色だった。
秋山沙耶は、役所の窓口当番を終えると、昼休みに傘を差して古い商店街へ足を向けた。細い路地に入ると、雨の匂いが一段濃くなる。屋根瓦を打つ雨が、軒下の樋を伝い、石畳に細い川を描いていた。
「西村古道具店」と手書きの看板が下がる店の引き戸を開けると、湿った木と紙の匂いが鼻をくすぐった。
棚には、使い込まれた湯のみ、銅の花器、古びたトランク。店の奥では、小さなラジオが天気予報を流し、主の咳払いにかき消される。
「いらっしゃい」
顔を上げた店主・西村は、六十をいくつか過ぎた温和な目をしている。
「雨の日に来るなんて、物好きやねえ」
「職場が近いので、つい……」
沙耶は笑って、入口脇の木箱を覗き込んだ。「葉書・一枚三百円」とマジックで書いてある。手に取るたび、紙が小さく鳴った。どれも古く、消印は昭和や平成の序盤。色褪せた観光地の写真、整った万年筆の字、丸い郵便の印。
一枚、異質なものが混じっていた。
宛名面の中心だけ、消しゴムか刃物で丁寧に擦られ、薄く白っぽい楕円ができている。周りの罫線はそのままなのに、宛名の欄だけが消えている。
「それはねえ」西村が口を挟む。「この前まとめて入った古紙の束に混じっててな。誰かが宛名を消したみたいや」
「どうして、宛名だけ」
「さあ。住所や文面は残ってるのに、宛名だけ。変やろ?」
雨音が少し強くなる。店の奥で、風鈴がからりと鳴いた。
沙耶は葉書を光にかざした。薄い紙の繊維が透け、擦られた部分の下に、かすかな鉛筆の影が見えたような気がした。
――秋山。
瞬間、胸の奥がひやりと冷えた。
見間違いだ、と言い聞かせ、もう一度角度を変える。文字の形は曖昧で、雨に滲む路面の揺らぎのように定まらない。それでも、最初の二文字目の縦画が、どうしても「山」に見えた。
裏面には簡素な文章がある。やわらかな字で、こう書いてあった。
「引っ越してから、町の色が薄くなった気がする。こっちは雨が少ない。そっちは、まだ降ってる?」
差出人名はない。消印は「高岡」。投函場所も、沙耶の町だ。
宛先の住所欄は無傷のまま、空白。あるべきものだけ、丁寧に消されている。
沙耶は財布から小銭を出し、葉書を一枚、レジ横の古い受け皿に置いた。
「これ、いただきます」
「ほう。気になるんか?」
「少し……」
西村は頷き、茶色の薄紙に葉書を包みながら言った。「宛名消しは、たまにあるよ。人に渡したくない時、名前だけ外したりな」
「渡したくないのに、葉書は残すんですか」
「捨てられん言葉ってのが、世の中にはあるもんや」
その言い回しに、沙耶は小さく息を呑んだ。捨てられない言葉。捨てたはずの名前。
店を出ると、雨は本降りになっていた。
役所に戻るまでの短い距離、傘の骨に当たる雨粒の音が急に近くなる。
信号待ちの間に、包みをそっと開いてもう一度、宛名面を光に透かした。
――秋山……さ……
次の瞬間、信号が青に変わり、背後から自転車が水しぶきを上げて脇を抜けた。葉書が風に煽られ、慌てて胸に抱き込む。
落ち着け。名前なんて、よくあるものだ。
午後の窓口は、住民票と印鑑登録の申請で途切れなく列ができた。
手を動かしながらも、脳裏には葉書の楕円が居座る。
ふと、古い記憶が指先を掠めた。高校二年の梅雨の終わり、郵便受けに挟まっていた見慣れない絵葉書。受け取ったはずなのに、文面が思い出せない。
――あれ、誰からだった?
机の脇に置いた私物箱の底で、携帯が震えた。兄・慎司からのメッセージだ。「今夜、雨やむなら寄る。伝票の件、相談あり」。
郵便局に勤める兄は、昔から天気と紙の機嫌に敏感だった。濡れた封筒が嫌いで、雨の日は配達区分の棚を何度も拭いていた。
“郵便と雨”。その組み合わせが、心のどこかをざわつかせる。
定時を過ぎ、窓口を閉める頃には、雨脚は少し弱くなっていた。
帰宅して玄関で靴を脱ぐと、兄からの着信が入っている。折り返そうとして、やめた。今は、葉書をもう一度見たい。
台所の明かりの下で、拡大鏡を引き出しから取り出し、楕円の中心をそっと覗く。
擦り痕は薄く、紙は毛羽立っている。そこに、微かに残る鉛筆のつや。
秋山――の後に、細い横線。
自分の名前の最初の一文字が、確かにそこにある気がした。
玄関のチャイムが鳴った。
覗き穴の向こうに、兄が立っている。雨合羽を脱ぎ、髪を手拭いで拭いながら、少しばつの悪い顔をしていた。
「悪いな、急に。伝票……の前に、少し見せたいもんがある」
慎司は肩掛け鞄から、封筒を取り出した。中から、四つ折りのメモと、小さな紙片が滑り出す。
紙片は、葉書の角のように見えた。端が丸く、消し跡に似た擦り傷がある。
「職場の整理で出てきた。だいぶ前のやつや。おまえ宛て……やった気がする」
沙耶の喉が鳴る。
「宛名は、どこ?」
慎司は視線を落とし、言いにくそうに口を開いた。
「……消えとる」
テーブルの上で、二枚の紙が向かい合った。
店で買った“宛名の消えた葉書”と、兄が持ってきた“葉書の欠片”。
二つの楕円が、雨上がりの窓の曇りのように、互いの輪郭を探り始める。
沙耶はゆっくりと息を吸う。
雨の日の葉書は、まだ何も語っていない。
けれど、宛名を消した誰かと、宛名に呼ばれた誰かが、同じ卓上に並んだとき、黙っていた時間はもう長くは続かない――そう思えた。
台所の窓の外で、雨が細くなった。
雲の切れ間からわずかに差し込んだ光が、紙の繊維を銀色に浮かび上がらせる。
削られた楕円の内側で、かすかに文字の影が揺れた。
――秋山 沙――
その先を読めるのは、たぶん、明日になる。
『消えた宛名』next>> 第2話 ― 消された記憶 ―
第8週『夕立ちの残響』<< Previous 第5話 ― 夕立ちの残響 ―
紙袋の行方
第1週 『見えない鍵』
第2週 『名前のない約束』
第3週 『宿帳の余白』
第4週 『買い取ってない品』
第5週 『願いは誰のもの』
第6週 『二人で書いた誓い』
第7週 『割れた陶片の先』
第8週 『夕立ちの残響』
第9週 『消えた宛名』

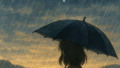

コメント